No.1 灘の酒が雲の上の存在だった
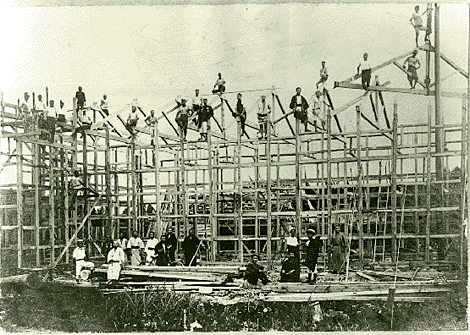
大正11年、酒蔵の建前で記念写真を撮る
東京から新潟へ向かう上越新幹線が越後湯沢の駅を過ぎてまもなく、車窓に広がる魚沼盆地の向こうに、越後三山の雄大な山並みが見える。越後三山とは八海山(1778m)、中ノ岳(2085m)、越後駒ケ岳(2003m)の総称だ。その中でも、八海山は古くから霊峰として知られ、山岳信仰の対象になってきた。
八海醸造株式会社の酒「八海山」の名前は、この山から取られた。蔵の所在地は南魚沼郡六日町長森。上越線の五日町駅から東に4kmほどのところにある。古くからの地主だった南雲家が、当時の城内村長森の地で酒蔵を始めたのは大正11年のことだった。
その最初の酒蔵の建前の時の記念写真が、南雲家に今も残っている。足に脚はんを巻き、半纏を羽織った数十人の職人が、梁や屋根の上で思い思いのポーズを取ってカメラに向かっている写真である。酒蔵を開いた故南雲浩一氏も写っている。建前は、たぶん、夏のことだったのだろう。浩一氏は浴衣のような涼しげな白い和服姿で、カメラに向かって笑いかけている。しかし、酒蔵を開いたのはいいが、決して順調な滑り出しではなかったらしい。
最初の酒蔵の経営は数年で行きづまり、昭和6年、自宅から1kmほど離れた今の場所に新たな酒蔵を築き、新規巻き直しを図った。浩一氏の息子で現在は八海醸造株式会社の会長の和雄氏は当時、数え年で4歳。その引っ越しの日の光景を今でもはっきりと覚えているという。「お袋が家の前の石に腰をおろして、ポロンポロン涙を流していた。心細くて泣いていたのか、それとも、別に理由があったのか。とにかく、何でお袋が泣いていたのか私にもわからないが、あの姿は忘れられない」
浩一氏は昭和28年に亡くなり、その後を和雄氏が継いで社長となり、さらに昨年秋、70歳になるのを前にして、和雄氏は会長に退き、和雄氏の息子の二郎氏が八海山としては三代目の社長に就任した。二郎氏はいま39歳である。
「二郎、お前が社長をやれ」
引き継ぎの言葉など、ほとんどなかった。和雄氏の「二郎、お前が社長をやれ」という一言で決まった。酒蔵で育った二郎氏には、それ以上の言葉は必要なかった。小さい頃の二郎氏の大好きな遊び場は、「八海山」の酒蔵だった。毎年、酒造りの季節がきて、できたての蒸し米でつくったひねり餅を貰える日が来るのを楽しみにしていた。アツアツの蒸し米を蔵人が手にとり、力いっぱい揉みながら作るのがひねりもちである。
腕白が過ぎたときは、仕込みタンクに放りこまれたこともある。もちろん、空になっているタンクだが。二郎氏は懐かしそうに言う。
「まだ小さい時だから、仕込みタンクに入れられると、いくらジャンプしても出られないんですよ。それでもピョンピョンと飛び跳ねている俺を、大人の人たちがタンクのふちに頬杖をついて、どうだ出られないだろうと笑いながら見ていたもんですよ。蔵の人間も社長の息子だからって遠慮してなかったなあ」
和雄氏も二郎氏とまったく同じように酒蔵を遊び場にしながら育った。大吟醸酒の仕込みの頃には、夜遅く、杜氏さんが重い足音を響かせて、まだ子供だった和雄氏の枕元を通っていった。それは大吟醸酒の仕込みタンクの様子を見にいく杜氏さんの足音だった。二郎氏は言う。
「うちのような小さな酒蔵は、良い酒を造る以外に、生きる道がない。また、それがうちの伝統だった。祖父も親父も、良い酒を造ることだけを考えて、酒蔵をやってきた。それがうちの誇りでもあるし、俺もそれを継いでいきたいと思っています。自分たちが納得できる良い酒をつくれば、その酒を飲んだ人は、きっと、うちの酒をわかってくれる。そう信じているんですよ」
三倍増醸酒に抵抗した
清酒「八海山」は人気の高い酒だ。いまや、需要に供給量が追いつかない状態になっている。酒蔵としては嬉しい状態だが、ただ、喜んでばかりもいられない。人気が高ければ、それに応える責任も果たさなくてはいけないからだ。経営学のような言い方をすれば、市場(マーケット)が存在するのなら、メーカーは全力を尽くして、その市場に製品を供給する責任がある-ということである。しかも、その製品の品質は今と同じ、あるいは、さらに高い品質のものでなければならない。それが八海山の考え方である。
現在、日本酒の消費量は全国で年間660万石(1石は1・8リットル瓶で100本)強である。そのうち、1%の消費者が良い酒を飲みたいと望んでいるとするば、それだけで6万石の市場があることになる。6万石というと、今の「八海山」の生産量の何倍にもなる。だが、蔵としても自信が持てるような品質が維持できる限りは、生産者の責任として、増産をしなくければならないのだ。
「八海山」には60人の蔵人がいる。生産量を考えるとかなりの数だ。ところが、ひとつの仕込タンクの容量は最大でも3トンと大きくない。本当に自信が持てる酒造りを頑固に守りながら、人手が必要なところには人手を惜しまずに、良い酒を造ろうとしているからだ。
良い酒を造りたいという強い思いは、浩一、和雄、二郎と「八海山」三代にわたって引き継がれてきたものだ。和雄氏は父親の酒造りを見ながら育ち、また、二郎氏も同じように育った。三代のゆっくりとした時間の流れの中で、酒造りにかける覚悟のようなものが、親から子へ、子からその子へと自然に受け継がれてきたのだ。
酒造りにかける覚悟とは、良い酒を造り続けるためには、あえて商売を度外視することも厭わないという思いきりのことだ。
和雄氏は「八海山」を開いた父、浩一氏の面影をこんな風に語っている。
「うちの親父がいつも言っていたのは、酒を造る時は損得など考えるなということでした。いつもそればかり。要するに明治の衆だったんですな。うちも戦後の食料不足の時は、国の命令で三倍増醸酒を造らなければならないことになり、親父はだいぶ抵抗していました。三倍増醸酒というのは、普通の純米酒に比べて、醪にアルコールとか糖類、酸味料を加え、通常の約三倍の量の酒を造ることですが、何しろああいう時代でしたから、結局、命令に従うことになった。その時の親父は本当に情けなさそうでしたよ」
解放農地が地域を潤す
八海醸造がある南魚沼郡は、コシヒカリの産地として知られ、冬ともなれば、上越新幹線や関越自動車道を利用してたくさんのスキー客がやってくる。しかし、大正から昭和初期の頃の南魚沼は、南は三国山脈で東京と隔てられ、コシヒカリもまだ生まれていなかったし、冬は深い雪の中に埋もれながら、春の訪れを待つしかない土地だった。
その地に「八海山」を開いた浩一氏にどんな成算があったのか。今風に言うなら、企業家ということになるが、決して商売一辺倒の人物でもなかったようだ。「損得など考えるな」という口癖も、その現れだが、さらに、戦後の農地解放の時、浩一氏が取った行動は周囲を驚かせた。占領軍が主導して行われた農地解放によって、全国の地主は持っていた土地を放出させられたのだが、山林は放出の対象外だった。しかし、浩一氏は戦争直後の地元の貧しい農民の窮状を見て、持っていた広大な杉林をたくさんの人に分け与えた。浩一氏が杉を伐採せずに土地を譲ったのは、それぞれ杉を売り払ったお金を資金として、開墾ができるようにするためだった。
その土地は浩一氏の狙い通り、次々に見事な畑地に生まれ変わり、その収穫で苦しい時代を乗り切った人も少なくなかった。その後、町が運動公園を建設するため、この土地を買い取り、今は畑地の面影はなくなっているが、運動公園予定地の一角には、浩一氏を偲んで入植者が建立した碑が今も残っている。
子供たちは貧乏な酒蔵を継ぎたがらなかった
南雲家自身も決して余裕があったわけではない。まだ酒といえば灘の生一本という時代で、「八海山」の名前は地元で知られているだけだった。「八海山」はさっぱり売れず、蔵の若い衆への給料も欠配こそなかったが遅配は珍しくなかった。
浩一氏には四男二女がいた。しかし、四人の息子たちも進んで「八海山」を継ぐつもりはなかった。貧乏な酒蔵を継いでも仕方がないと思っていたようだ。あるいは浩一氏も同じ思いだったかもしれない。長男には医師になって家を出ることを許し、二男は請われるままに婿に出した。三男は東京に出て化学肥料を海外に輸出する特殊法人に就職して六日町を離れた。さらに四男で末っ子の和雄氏まで、婿にこないかという話が持ちこまれた。
和雄氏の養子話は和雄氏自身が断ったため流れたが、上の兄たちと同じように、和雄氏にも家を継ぐ気はまったくなかった。東京農大に進学した和雄氏は、山岳部に入って山の魅力を知り、卒業後は北アルプスを望む長野県大町の営林署に就職する話を進めていた。しかし、浩一氏が体調を崩したため、急遽、和雄氏が家に戻ることになった。
昭和26年、農大を卒業した和雄氏は六日町に戻り、5月、三島郡和島村の木村家から仁(あい)さんという嫁を迎えた。木村家も代々の地主で、良寛が最後の日々を過ごした家として知られている。良寛の墓がある竜泉寺を建立したのも木村家である。仁さんにその頃の日々を話してもらった。
「私は嫁に来た次の日から、お酒の瓶詰をさせられましたよ。だけど、その頃は、木村の家も農地解放で苦しくなっていたし、みんなが貧乏だったから、お酒の瓶詰をしたり、瓶洗いをさせられても、特別に辛いとも思わなかった。お父さんはお祖父さんにひどく叱られた後など、やっぱり営林署に行ってればよかったかなあ、なんて、こぼしてたこともありましたけどね」しかし、貧乏と言っても、六日町では裕福なほうだった。お金はなくても酒さえあれば、酒と交換でだいたいのものは手にいれることができた時代でもあった。
昭和30年当時、蔵にいたのは杜氏さんのほか10人程度。今は「八海山」の製造部長として蔵の酒造りの指揮をとる高浜春男氏は、昭和34年から杜氏をしている。新潟県の漁港寺泊に近い野積(のづみ)を本拠とする野積杜氏の一人である。その頃の高浜氏は、毎年、11月の初め頃になると、蔵人たちを引き連れて、「八海山」にやってきて、酒造りが終わる4月には、また野積に引き上げていったものだ。春が来るまでの間、この杜氏さんや蔵人たちの食事の世話をするのも仁さんの仕事だった。
良い酒造りに意地を張る
「八海山」の年間生産量は今では2万石だが、当時は300石とごくわずかなものだった。1石は一升瓶にして100本である。300石というと、当時の設備でも、一カ月もあれば仕込みが終わってしまう程度の量だ。
ものがない頃だったから、酒と名がつけば何でも売れた。しかし、まだ知名度もなく、有力な販売ルートもなかった「八海山」は苦戦した。
「うちの酒は今は需要に供給が追いつかない状態で、どうやって、求めに応じられるだけの量を造れるか頭を悩ましている状態ですが、そんな時が来るなんて、もちろん、当時は想像もできなかった。当時の私らにとって、全国的な知名度を持って商売をしていた灘の酒は、文字通り、雲の上の存在でした」
と和雄氏は振り返る。しかし、酒の良さでは大手にも負けないという自信まで失うことはなかった。
当時の酒造りでは醪を発酵させる期間は、20日前後が普通だった。中には、生産量を増やすため、10日で発酵を終わらせてしまうなどという酒屋もあった。しかし、「八海山」では、この当時も一カ月近くかけて、この土地の気候と水にあった長期低温発酵の酒造りをしていた。雪に埋もれた「八海山」の酒蔵では、毎年、毎年、まるで意地を張るためだけに酒を造っているような日々が続いた。
「あらたまった祝い事なんかでは、やはり灘の酒を使わんきゃならんが、晩酌の酒は、やっぱり、おまさんのところの酒がいいよ」
地元の六日町にはそんな風に言ってくれる人もいた。この頃の和雄氏にとっては、そんな風に言ってくれる人がいることだけが慰めだった。
※文中に出てくる肩書き、年齢は当時のものです。
記 1998年 井出耕也[インターネット・パイロット]
- この記事をシェアする
-
